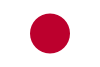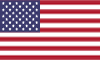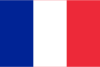Stats
| スピード |
|
0 |
Related Collectible
Lore
パラダイムシフト
あまりの速さに新たなバリアを開発する必要がある。
「彼女のことは二度と口にするな」オシリスは怒りながらエクソのタイタンに言った。彼の声が騒々しいハンガーに響き渡った。
数十メートル先のジャンプシップの影の中で、クロウとホリデイが同時に顔をしかめた。彼らは船から下りたばかりだったが、もしクロウの反応が遅れていたら、この口論のまっただ中に足を踏み入れることになっていただろう。諜報活動をしていたおかげで、私的な会話に対する彼の第六感は誰よりも発達していた。現場だけでなく拠点でもこの能力の有効性が証明されたのはありがたいことだった。
「ああもう」怒って出て行くオシリスを見ながらホリデイが呟いた。クロウは説明を求めて彼女を見た。このエクソの正体は? 初めて聞いたその「彼女」とは誰のことだ?「後で説明してあげるよ」と彼女は囁くと、遮蔽物の後ろから出た。
「ホリデイ!」クロウが慌てて言った。だが遅かった。彼女は既にエクソの横に並び、同情を示すように彼の肩に手を置いていた。
彼は足の前後を入替えながら、自分に与えられた選択肢の重さを量った。物事がいたって順調に進んでいたとしても、新たな状況が訪れる度に彼は不安を感じていた。タワーではほとんどのガーディアンがマスクをつけておらず、会話に加わりたいという気持ちもあったが、自分の顔を見せたらどうなるかはしっかりと理解していた。それでも、マスクをつけている時間が長くなればなるほど、自分が余計に注目を集めているような気がしてならなかった。いずれは疑念を呼び起こすだろう。
だがそうとも言い切れない。エクソはヘルメットをかぶっていたが、ホリデイは最近クロウと出会ったときと同じように、特にそれを気にしていないようだった。
そもそも、永遠にマスクをかぶり続けるのと影の中でコソコソし続けるのは、どちらのほうがより怪しまれるだろうか? クロウは階段の下から出ると平静を装った。彼が近づくとホリデイの声が聞こえてきた。「私に何かできることがあれば言ってね?」
彼らが何を話しているのかを考え始めた瞬間、エクソが彼のほうを向き、雷鳴のように言った。「で、彼は? 体は細いが動きが力強い。恐らくハンターだな」
用意していた当たり障りのない挨拶の言葉がクロウの頭の中から消失してしまった。喉をつまらせ、彼が無言のままうなずくと、ホリデイが笑いながら彼の背中を叩いた。
「彼はクロウ。カバル関連の全ての情報の提供者だ」と彼女が言った。「。クロウ、彼はセイント14。彼は… その、色々な仕事をしてるけど、主にオシリスの試練の管理をしている」
今回に限っては、彼はマスクに感謝した。マスクがなければ、その名前に驚いたことに気付かれていただろう。彼はその名前を知っていた、当然だ――ここでは称賛と共にその名が語られ、入り組んだ岸辺ではその名は嫌悪の対象となっていた。彼の腕を掴んでいるこの陽気なタイタンには、そのどちらも当てはまりそうにない。
彼のスパイの本能が再び彼を救った。「そうなのか? それは興味深い」クロウはそう言うと、少し力を込めて同じように彼の手を掴んだ。「試練という名前でしか聞いたことがなかった。オシリスが関係しているとは知らなかった」
セイントは残念そうに笑いながら手を離した。「彼は数多くの重要な任務に関わっている。私は自分のできる範囲で協力している」
「あなたの協力があってこそよ」とホリデイが正した。「彼はあなたに感謝すべきよ」
クロウはセイントを見た。オシリスが他人に感謝する姿は想像したこともなかった。
「協力に感謝は必要ない。我々は見返りを期待せずに、互いを高め合うべきだ。バンシーは例外だがな」と彼は、こちらにウィンクするかのように付け加えた。「彼にはグリマーの貸しがある」
クロウは笑った。もはや警戒心など失われていた。彼はここまでセイントに気を許している自分に驚いた。そして同じように彼に好かれたいと感じていた。ここまで親しみやすい人物とオシリスのような威圧的な人物にどのような共通点があるのだろうか?
彼の思考の外で、ホリデイの話し声が聞こえる。彼は彼女の話に意識を戻した。「…お互い様だってことよ。そう思わない?」
突然、セイントの態度が変わった。「私はそうは思わない。戦場では、戦友がつまづいたら、彼らが立ち直るまで彼らを背負わなければならない。自分が怪我を負ったとしてもだ。そうしなければ前に進むことはできない…」
彼の言葉がクロウの琴線に触れた。セイントとオシリスはかなり古い付き合いなのだろう。こんな風に安心して誰かに自分の背中を任せられるのはどんな気分なのだろうか? 同じ大義のために一緒に戦うのはどんな感覚なのだろうか? 彼はそれを知りたくてしかたなかった。
「話せてよかった、ミス・ホリデイ。お前もな、線が細いクロウ」とセイントは皮肉を言うと、その場を後にした。
クロウは、群衆を軽々とかき分けていく大きな背中のタイタンを見つめた。「お会いできて光栄だ」と彼は弱々しく言ったが、既に声の届かない距離にいた。
ホリデイが笑った。クロウは彼女に視線を向けた。今なら何が起こっているのか説明してくれるだろうか?
彼女は首を振った。「長い話になる」と彼女は言うと、彼の肩に腕を回した。「酒を飲みながらじゃないと話せない。今回はそっちの奢りでいいね?」