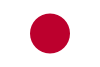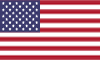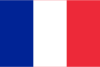Related Collectible
Lore
追悼のシェル
光の道標であるゴースト用。
タワーのハンガーは今までも決して静かな場所とは言えなかったが、今日の騒音は記録的だった。ファイアチームが次々と数多くある戦場に向かって飛び立つため、ジャンプシップの轟音が止むことがなかった。
幸いにも、セイント14はそれを上回るほどの声音を誇った。「ようこそ、ガーディアン!」灰色バトの横のいつもの場所に立ち、試練を求めるものたちを意気揚々と迎え入れ、まるでひとりひとりに対して旧友と再会するかのように挨拶した。
だがその陽気さには不安も見え隠れしていた。ピラミッドが到来したことで胸の内の線がピンと張り詰めた。最近起こった試練での事件以来、彼の緊張感は日を追うごとに増し、着々と限界点まで到達しつつあった。
事件は前にも起きたことがある――ガーディアンが衝突する時はそういったことが予想される。重要なのは、そういった激論を統制できる環境に制限することだった。それでも最近は、果たして自分は統制できているのだろうかとセイントは疑問を抱いていた…
だがそういった疑念に飲み込まれそうになった瞬間、群衆が分かれてその間を見覚えのある黄金のフードを被った人物が歩く姿を見た時に、負の感情はすっかり晴れた。彼の周りをサギラが飛び回っていないせいか、いつもより猫背気味のように見えたが、意志の固さを物語る歩みと、しわの寄った眉間は… 以前と変わらなかった。
「オシリス!」セイントが叫んだ。急に叫んだことに驚き、数名が彼のほうへ振り向いた。オシリスと言えば、少し困惑した表情を浮かべて進路を変えた。
「どうしたんだ?」オシリスが近づくと尋ねてきた。「何か起きたのか?」
「いや」セイントは素早く答えた。不自然なほどに早い返答だった。「まあ… ちょっとな。大したことでもないんだが…」自分でもどう説明して良いかわからず、思わずどもってしまった。「メッセージを送信したんだが、届いてないか?」
オシリスは苛立ちを隠せずにしかめっ面を見せた。「最近は送られてくるメッセージが多くてな。緊急を要する内容か?」
セイントはビクッとした。緊急だったのか自分でもわからない。「試練のことだ。オシリスの名の下に行われているんだし… 本人がここに戻ってきた今…」
「ああ。私に試練を執り行ってほしいということか」オシリスは肩をすくめた。「タイミングが悪い。手に負えないなら打ち切ってやれ」
「何だと? それはダメだ!」セイントはそんな返答を想像していなかった。「手に負えないわけじゃない。心配なんだ! これまでに――」通行人の存在に突然気づき、話すのを中断した。彼は船の中へついてくるようにオシリスに合図した。
オシリスは腕を組んだ。「こうしている間にもサラディン卿を待たせている。カバルの問題は至急解決しなければならない。言わずもがなだがな」
「分かっている…」セイントは静かな声で話した。「だが、試練の中でも紛争が起き始めている。ガーディアンたちの歯止めが利かない。暗黒の力を使い始めている」
「本当か?」オシリスの目は新たに芽生えた好奇心で輝きだした。「それで、どんな影響が?」
セイントは彼を見つめた。これ以上は無理と思われた緊張の糸がさらに張り詰めた。やっとの思いで「いろいろだ」と答えた。
「興味深いな」オシリスが思案しながら顎をさすった。腰に取り付けられているデータパッドが通知音を鳴らした。彼は唸り、セイントのほうへ振り返った。「また起きるようであれば詳細を書き留めておいてくれないか?」
返事を待たずに彼は去ろうとした。セイントの鉄の腕が伸び、彼の肘を掴んだ。
「お前にとってはその程度のことなのか? ただの実験か?」セイントは口走り、声を抑えようとする努力も虚しく荒げてしまった。これ以上自分を抑えることができなかった。もう何日も彼からの応答を待っていた。沈黙に焦りを感じながらも、せかさないよう配慮した。「ならば私はお前にとって何なんだ? 助手か? サギラがいなくなったからといって――」
「もういい」オシリスは怒鳴り、腕を振りほどいた。「彼女のことは二度と口にするな。いいな?」
セイントは後ずさりし、すぐに後悔に苛まれた。考えがまとまらない。この状況を少しでも良くするために、何かを、何でもいいから言うべきだった。正しい方向へ戻すために。だが、何と言えばいい?
答えを思いつく前にオシリスが口を開いた。「試練を続けるか続けないかはお前次第だ。データを収集する根性がないなら、誰か他の奴に頼め。我々の生存の鍵となり得る。全員のな」そう言い放ち、彼は出て行ってしまった。
セイントはオシリスが群衆の中へ消えていくのを眺めた。彼の中の緊張感はもはやなくなっていた。残されたのは、限界点まで達した線がちぎれた時に生じる苦痛だけだった。
しばらく前にイコラが言った言葉が頭をよぎる。「…あなたは誰よりもオシリスのことを理解している」
嘘だ。セイントは彼のことを良く知っていたが、サギラほどではない。そして彼女がいない今となっては…
オシリスが赤の他人のように思えた。