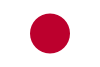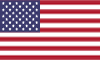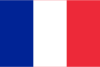Special Perks
栄光の残響
このセットのクラスアイテムはアーマー{var:1637760185}個分の効果を付与する。
Stats
| 防御力 | 0 |
Curated Roll
Lore
属さぬ刃のガントレット
しっかり握れ。
セイント14がベックス・ゴブリンを頭上に掲げると、ゴブリンは金属の四肢をばたつかせた。タイタンが唐突に片膝をつき、暴れるベックスをその隆々とした膝に振り下ろすと、中核にあるレディオラリア容器にひびが入った。
セイントのブーツにレディオラリアが滴り落ち、ベックスの赤い瞳がちらついて消える。彼は満足げに立ち上がり、死んだフレームを無造作に捨てた。
「見たか?」彼は明るい声で聞いた。「奴の体重を逆手に取ってやったぞ!」
「おおー」通信から聞こえるのは、フェールセーフの低い感心したような声。彼女はセイントの視覚映像に釘付けだった。彼女が自身のフィルターを調整すると、その口調は陽気なものに変わった。「もう一度見せてください!」
「いつでも接近戦に持ち込めるわけではないが、こうすれば銃弾の節約になる」セイントが言った。彼は手に付いた土埃を払い、笑った。「ベックスを破壊するのは実に爽快だ! ストレス解消になる!」
「なるほど、わかった気がします!」フェールセーフが甲高い声で言った。「あなたはこの致死的な表現によって起こされる力の転換のおかげで、社交フィルターを長時間起動し続けることができるのですね?」
セイントがヘルメットを脱いでも、通信は途切れることなくエクソ内蔵のイヤホンに伝達された。「どういう意味だ?」
「聞き方を変えますね」フェールセーフが返事した。「あなたのプロセッサーの何%程度がポジティブな態度の保持に充てられていますか?」
セイントはネッススの地表に露出した岩石に向かって目を細め、ヘルメットを手の中でひっくり返した。「フェールセーフ」彼は丁寧な口調で話し始めたが、彼女が割り込んだ。
「もう、わかったよ」彼女は呆れたように言った。「つまり、あんたはさ、とにかくいつも陽気でさ、だからハッピーバンクを酷使してるんじゃないかって話」
セイントが満面の笑みを浮かべた。「エクソはAIとは違う。私は私だ、フェールセーフ。私でいるために、余分にやらなければいけないことなどない」
「わあ!」少ししてからフェールセーフが叫んだ。「それはとっても素晴らしいですね!」彼女のはつらつとした声は嫉妬を隠せていなかった。
「お前の場合は違うのだったな」セイントが言い、ヘルメットをなだめるようにポンポンと叩いた。「だがお前も、友と話す時くらいは余計なパワーを使わなくてもいいと思うぞ」
通信に重い沈黙が流れる。
フェールセーフの声は小さく、遠慮気味だった。「セイント?」彼女は静かに言った。
「何だ?」
「ケルを頭突きしたことはある?」
セイントが思わず吹き出した。「私はあらゆるものに頭突きをしてきたぞ!」
「あんたのファイルを確かめてるんだけど、うん、確かに頭突きしまくってる」フェールセーフが言った。彼女はセイントの膨大な量の功績をスクロールしていった。そのすべてには彼の視覚映像が添付されていた… ただひとつを除いて。
「おかしいな… セイント、VanNetに未確定の報告があるよ。去年、サバスンの玉座の世界で無許可な単独任務をしたって書いてある。これによると――」
「その報告を記録した者は?」セイントが聞いた。
フェールセーフがVanNetのプロフィールにアクセスすると、無数のアカウントフラグが表示された。「制限されまくってるアカウント、_MRU_って人がその場にいたんだって」
「くだらん」セイントが否定的に言った。「システムの報告すべてを信用できるわけではないからな」彼はヘルメットを被り、ベックスが出現し始めている煌めくレディオラリアの流れに向かって足を進める。
フェールセーフはセイントの微妙な口調の変化に気づいた。その会話は、突然彼にとって不愉快なものになったようだ。
誠実さを管理する部分にエネルギーがいっていないのだろう、とフェールセーフは思い、その話を続けなかった。