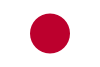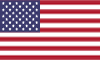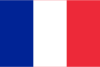Related Collectible
Lore
総督のヘルム
「過去は過去でしかない。戻ることはできない。今できることは、皆にふさわしい未来のために、刃と血でもって戦うことだ」――バルス・カウトゥール
カウトゥールは、ヴァラックの花の柔らかい繊維を手でなぞりながら歩く娘を見ながら笑みを浮かべた。彼女が通った後には、生物発光性の花粉が日没の光の中を舞う。カウトゥールは目を閉じると大きく息を吸い込み、雨期の始まりを告げるその強い香りを大いに楽しんだ。
「どうして私をここに?」彼の娘が聞いた。娘が話している間も、カウトゥールは記憶にある娘の姿を思い出していた。小さな子供が明るい色のローブを身に纏いながら飛び回っていた。彼が目を開けると、大きなバトルスーツを身に纏った成熟した戦士の姿がある。
彼は彼女の腰にぶら下がっているメッキ加工されたブロードソードを示した。「今朝、厳しい訓練を行なったと書記官から聞いている」
「私の剣は飽くことを知らない」と彼女は答えると、武器を抜き、ふざけてそれを父親に向けた。彼女が笑顔を若干曇らせた。「直接見ればよかったのに」
カウトゥールは努めて平静を装った。「すぐにその機会は訪れる、タナム」
タナムは剣を鞘にしまった。カウトゥールは甲冑で乾いた草と花弁を踏み潰しながら娘に近づくと、肩に手を置いた。
「それで結局何の用だ? 戦争前夜に故郷の思い出話か?」とタナムは聞いた。
彼女の父が笑った。「そんなに思い出が大切か?」
タナムがしかめ面をした。「毎日、懐かしく思ってる」
「誰でもそうだ」と深いため息をつきながら彼女の父は言った。「とにかく。お前にはそれを直接目にできる最後の機会を与えたかった」
タナムは振り返ると眉をしかめた。「最後の機会?」
「もう十分だ」とカウトゥールは言った。体中の骨に低い音が反響し、景色が変わった。遠くの山が波打ちながら空まで伸びていき、花々が突然、浮遊して泡の雲へと姿を変えた。世界が不明瞭になり、光と物質が粘度の高い液体のように、大きくなる空の裂け目へと吸い込まれていき、それを完全に飲み込むまで影が大きく広がっていった。
彼らはバルバトス・レックスの中で目を覚ました。船はまだ星々の中を進んでいた。彼らの手は錆びた剣の持ち手を握りしめていた。1人のサイオンが近くに立っており、3人を繋げていたサイオニックエネルギーのおぼろげなツタが姿を消した。
カウトゥールはサイオンに向かってうなずいた。「2人にしてくれ」
「理解できない」と2人きりになるとタナムはすぐに言った。
カウトゥールは剣を高く構えた。「4世代前、この武器は我々の一族に帝国内での居場所をもたらした。その歴史は、精神の旅の中で、強固な中核的役割を果たしている」彼はそう言うと、刃を慎重に眺め、その重さの配分を確かめた。「だが歴史とは勝者の贅沢品に過ぎない」
カウトゥールはその武器を両手で持つと、それを半分に折り、ガントレットでその破片をすり潰した。
タナムは少し後ずさりした。「父さん…」
「これが生まれた世界は今や姿を消した」とカウトゥールは続けた。「もはや後ろを振り返っても故郷はない。それは今、そびえ立つ山を越え、大いなる海原の向こう側の、遙か遠く前方に存在している」
タナムはうなずいた。「我々はカバルだ。山を喰らい、海を飲み干す」
カウトゥールは体を乗り出した。「だが、都合の良い空想をして飢えを癒やしているようでは、この未来は実現できない。だから我々がこの手の思考に興じることは二度とない」
タナムは体をこわばらせた。「なるほど」
「太陽系には我々の仲間が眠っている。だが、彼らは我々の街が魂の炎で焼かれる姿を見ずに済んだ。故郷の思い出を慰めとせず、その傷の記憶を怒りの糧とするのだ」
タナムはうなずいた、ただ感情のしこりが彼女の口を開かせた。「奴らを恐れているのか? 太陽系の戦士たちを」
カウトゥールは誇らしげに笑うと、娘の手を取った。「そんなことはない。なぜなら、タナムが一緒に戦ってくれるからだ。タナムの剣は飽くことを知らない」