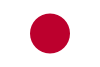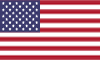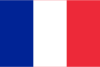Related Collectible
Lore
宇宙遊泳のグラスプ
アーカイブ | カストル | 231 | ――理解できない。コード・インジェクションはみんなが楽しみにしていることだが、シャーシに入れるのはまだ早い――
到着から17日が経過した。
カルルホがいつも話している大物のバンダルやマローダーはヤラスキスには目もくれないほどの大物だった。彼らは施設で見つかった人間の古い設計図を基に、共同でエーテル精製装置を建造していた。カルルホが彼女と話すことはもうほとんどなかった。
ヤラスキスはエンジニアには向いていなかった。繭の中にいた頃、彼女は司祭ではなくキャプテンになることを夢見ていた。彼女は使い走りをしたり、物を運んだり、誰も近寄ろうともしない古い染みの掃除をしたりしながら施設の生活環境の改善に励んでいた。
彼らの我が家は日に日に穏やかな生活音で満たされていった。プラットフォームを繋ぐケーブルがきしむ心地良い音。足巻きと爪が床に触れた時のトン、カチッ、トン、カチッ、という音。そしてクルーの中でサービターのコードを理解できるたった2人の船員が口論する音。
頑丈な巣穴とまではいかないが、安全であればそれで十分だった。そこにエーテルが流れ始めた時には、また一段と快適になるはずだ。
ヤラスキスは施設内放送をなるべく聞かないようにしながら、焼却炉のような機械の中にぼろきれを投げ入れた。
背後から誰かにフードを引っ張られ、彼女は叫び声を上げた。彼女は腕を横に振るが、よけられてしまう。
カルルホだ。「話がある。何かがおかしい。パスキルが見つからない」
パスキルはバンダルにしては大柄なエンジニアだった。あまりにも図体が大きかったせいでキャプテンに挑戦者として目を付けられていなければ、パスキルは彼らとケッチを盗むことに同意したりはしなかっただろう。
「迷子になったのかも。それかネバネバにはまって動けないのかも」人間がこの施設で何をしていたのかはわからないが、液体が… 大量に使われていたことだけは確かだ。ヤラスキスは毎日最低でも5回は手を消毒していた。
「原子力供給の仕事を手伝ってもらうはずだったのに結局来なかったんだ。それに、廊下で音が聞こえた」彼女の表情を見たカルルホが補足する。「あれは相当でかい何かだったぞ!」
「相当でかいんだったら、私たちがここにたどり着くとっくの昔に飢え死にしていたはず。どうせ無重力エリアで足止めをくらってるんだろう。そのうち助けてくれって連絡してくるよ」
「探すのを手伝ってくれるか?」
彼女はカルルホの肩に1本の手を回し、彼を焼却炉モドキから遠ざけた。
「朝までにあいつが恥ずかしい話をひとつ増やして戻ってこなければ、みんなで捜そう」
カルルホはエンジニアリングをこよなく愛している。彼はサービターの司祭やスプライサーになるべきだ。ヤラスキスはキャプテンになって、彼を司祭にすることを望んでいた。天井に頭が触れ、クルー全体を腕で包み込めるほど大きくなることを望んでいた。
ハウスよりもここにいるほうがいいはずだ。
そうでなければならない。