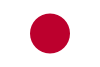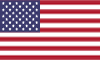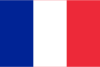Special Perks
Stats
| 威力 |
|
92 | |
| 射程距離 |
|
65 | |
| • Damage Falloff | |||
| 安定性 |
|
32 | |
| ハンドリング |
|
34 | |
| リロード速度 |
|
30 | |
| • Reload Time | |||
| 照準補佐 |
|
66 | |
| 所持品のサイズ |
|
55 | |
| ズーム |
|
14 | |
| 空中効果 |
|
23 | |
| 反動方向 |
|
95 | |
| 毎分発射数 | 120 | ||
| マガジン | 8 | ||
| 攻撃力 | 0 | ||
Curated Roll
Lore
イグニアス・ハンマー
炎と力によって鍛えられた。
「やりたくないならしなくてもいい」イコラが言った。「気持ちは分かる」
図書館の反対側でオノールが睨む。穢れたガーディアンを追跡するという不快な任務に身を捧げており、彼女は潜みし者の中でも最も献身的な人物の一人であるといえる。しかし、だからこそイコラは心配だった。会うごとに彼女はどんどんやつれていっている気がする。ちょっとしたことで怒る。この聖戦のせいで疲弊してきているのだろうか? 彼女に休息ではなく新たな任務を与えることは間違いだったのだろうか?
「私は約束を守る」オノールはトランスマットする前にぴしゃりと答えた。
そう言われたところでイコラの不安は一向に改善されなかった。彼女はため息をつき、こめかみを撫でた。
だが、彼女にはあまり考えている余裕がなかった。また空気が割れるような音をたてた。イコラが目を開けると、先ほどまでオノールがいた場所にセイントが立っている。「イコラ・レイ、突然来てしまって申し訳――」
「どうやってここに?」彼女は思わず言った。潜みし者以外、彼女個人の図書館の場所は知らないはずだ。彼女はそう思っていた。
エクソは困惑した様子で彼女を見つめた。「ト――トランスマットで来たんだが」とあっさり答えた。もう一度話しかけようとした。「申し訳ないが、話したいことがある」
「いいえ、誤るのは私のほう。座って」彼女は肘掛け椅子の周りに積みあがっていた本を急いで片付けた。「あなたからのメッセージは受け取った。2回も同じことが起きたのは残念ね」
セイントが座ると、彼の巨大な体躯に比例して椅子が小さく見える。「確かに残念だ。不気味でもある。私は恐れている…」彼は言葉に詰まり、目を逸らす。窓の外を見ると、午後の光が黄金色に変わり、空に沈みはじめていた。「戦場では何をすればいいのか確信が持てる。迷いはない。試練もそうだった。だが、今はどうすればいいか分からない」
「よく分かる。私も、こういう事は私たちの能力を含めてあらゆるものを疑うために起きるんじゃないかとたまに思うことがある」イコラが彼の隣に座った。「だけど、こういう時に試練を任せられる人はあなたしかいない」
「試練にその名が与えられた者でも駄目なのか?」セイントは悲しそうな笑いを漏らす。「いずれにしても、あいつはやりたがらないが。尋ねても、忙しすぎるからとすぐに拒否される。手に負えないなら打ち切れと言われた」
「確かに彼は忙しい。カバルのゴタゴタで、3人目のバンガードのように動き回っている。だがカイアトルとの件が落ち着けば、もしかしたら…」
「そうじゃない。私は彼が忙しくてホッとしているんだ。忙しいのは良いことだ。失ったもののことを考えずに済む。だが、それでも彼は…」
「前とは違う?」
「いや。そうなんだが、それだけじゃない」彼は苛立ちで首を横に振った。「例の件について報告した時に、私と同じように心配するかと思った。だがその代わりに、次は詳細を書き留めてておいてくれと言われた。使えるデータが集まるだろうって」と、嫌悪に満ちた言い方で答えた。
イコラは話の続きを期待するようにセイントを見た。何も言わないと分かると、彼女は自分の席にまた深く座り、考えた。さして驚くことではなかった。オシリスは実験主義的であったし、気を遣うようなタイプでもない。いつもよりトゲトゲしい発言ではあるものの、セイントがなぜそんなに気にしているのか分からなかった。まるでオシリスに怒っているかのように気が立っている…
「あれだけ色々あった後なら、そんな風に言われて腹が立ったでしょう」彼女はゆっくりと話した。彼女の考えを肯定するかのように、セイントは目を逸らした。「でも彼が言うことも一理ある。私たちは暗黒についてあまりに無知すぎる。データは多ければ多いほど有利になる」
セイントは何も言わなかった。窓から入ってくる光が彼のヘルメットをオレンジ色に染める。
「だけど」彼女は続けた。「そのためにガーディアンを危険な目に遭わせるべきではない。今オシリスがどう考えていようと、試練はファイアチームを鍛えるために始まったもので、その目的は今後も変わらない」彼女は立ち上がり、片手をエクソの肩に置いた。「絶対ね」
彼は地平線を見つめたままうなずいた。「そうか」