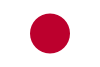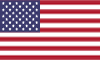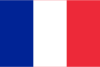Related Collectible
Lore
遺産の誓いのヘルム
「人生はタイミングがすべてだ。いつ引き金を引いて、いつキスを求め、そして何よりも、いつ逃げるべきかを知る必要がある」――ケイド6
シティの遥か上空、タワーに数多くある小部屋のひとつの中で、ケイド6は古い本に目を通していた。預言者の図書館から引き出した書物は経年劣化により破れやすくなっているだろうと彼は思い、1枚1枚丁寧にページをめくっている。触覚は問題なかった。金属の指には非常に精密な射撃を繰り出せるほど十分な回路が張り巡らされている。それでも、微かに触れただけで脆い紙を破いてしまいそうだった…
ケイドはあるページで手を止めた。「船乗りが語り奏でれば、嵐と冒険が、暑さと寒さが――」
突然、驚くほど冷たい風がケイドの手から本を吹き飛ばしかけた。「こんな呪われた氷は崩れてしまえ!」と彼は叫び、腰かけから転げ落ちそうになった。
彼は姿勢を正して深呼吸をする。気を確かにしろ、ケイド。呪われていようがなかろうが、お前は氷の上にいるわけではない。お前は地球に、シティにいるのだ。
だが、まるでカメラのフラッシュの後に数秒見える光線のように、記憶が残存する。春か遠くの月の雪のような平原、氷と鉄の棺。
—閃光—
エクソサイエンスの工場の外にある浜沿いに貨物を次から次へと積むケイド1にとって、エウロパとはそういうものだった。空でさえも平坦な灰色に変わり、下に広がるもの全てに影を落とし、光を殺してしまう。警告の空だ、と彼は思った。船乗りたちの歌でそういうものがあった気がする。
いずれにせよ、働く気を削いでしまうような環境だった。ケイドは貨物のひとつに腰掛けた。「休み時間だ」と彼は声をかけた。「必要かどうかにかかわらず、昔はこの時間に昼食を食べた。昼休みの間は働きたくはない」
隣でノックス4が安堵と渇望のため息をつく。「昼食がなつかしい。腹が減る感覚もな」
ケイドは機械の顔面が許す限りの笑顔を浮かべた。「ふむ…」とアブラム博士の真似をしながら喋りだし、「つまり… 飢えることに飢えているということか?」
ノックスは堪えきれずに爆笑した。ケイドは弱々しく鼻で笑った。そんなに面白くはない。だが友の笑い声が大きくなるとともに、ケイドもつられた。やがて、2人は互いを掴んで大笑いした。
そして徐々に2人の喜びが弱まった。「ところで、あの『精神科医』のことをどう思う?」とノックスが尋ねた。「ささやき声については話したのか?」
ケイドは頭を横に振った。精神科医の意味の無さについて皮肉を言う前に、彼の金属の頭に囁きが響き始めた。赤い空模様の朝、船乗りの警告だ。だが自分は船乗りではない。
荷積み場からすすり泣く声が聞こえてきた。そして、スノースーツを着た背の低い何者かが飛び出し、工場の反対側へと逃げて行った。ケイドとノックスが叫び、盗み聞きの犯人を追い始めた。まだ狙撃を会得していないケイドはブレイ・テクに至急された拳銃を探り、震えながら照準を合わせ…
—バンッ—
ケイド6は隠れ家に戻るとやっと我に返った。戦利品の山を探っていると… 「あった!」彼はペンを見つけた。これで終わりではない。彼は本を開き、今度はページを無遠慮にめくり、殴り書きし始めた。
「我々と同じような体験をしてきたエクソと一緒に過ごせば、聞いてきたことが見えてくる…」