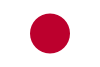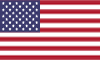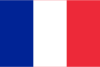Stats
| 防御力 | 0 |
Lore
ピュロスのグローブ
「私は赦されざる存在だ」――アウォークン・ウォーロック、シャユラ
シミュレーション再構築ログ//LA-03-03//シティ、タワー、バザー
罪の意識と羞恥心がスペクトラルブレードのようにシャユラの心をかき乱した。ニューモナーキーの真紅の装飾の下で、彼女は座りながらテーブルの天板の木目を凝視していた。自分の呼吸音がまるで騒音のように感じた。だがそれと同時に、まるで水中にいるかのように、周辺の群衆の音はくぐもって歪んでいる。
「気分はどうだ?」
シャユラには自分の呼吸音以外はほとんど聞こえていなかった。彼女はさらに前屈みになると、手で髪をかきあげてテーブルに両肘をつき、過去に引き戻そうとする自らの精神に抗いながら、必死になって現在に食らいついた。
「イコラとはまだ話してないのか?」
新たな罪の刃が突き刺さった。シャユラは何か言おうとしたが、喉が渇ききっていた。ここにたどり着くまでにエネルギーを使い果たしていた彼女は、自分のことをより無価値に感じていた。
「まだだ」とシャユラはようやく言った。意識がはっきりとせず、反応も遅れていた。「話すつもりではいる。」と彼女は約束した。なぜならそれがアイシャの聞きたい言葉であることを知っていたからだ。「すまない」
「謝る必要はない」とアイシャは言うと、しばらくしてからシャユラの肩に手を乗せた。その物理的な接触はまさに存在の証明であり、それが彼女を現実世界に引き戻した。「当然だ。私たちは多くの困難を体験した。対戦に参加する前に、シャユラがどれだけ苦しんでいるか、もっと気を付けて見ておくべきだった。それを知らずにすまなかった。怒鳴ってしまったことも謝る」
アイシャの悲しげな声は救済であり苦痛でもあった。疲れ切っていたシャユラは体を沈み込ませた。自分の欠陥が原因で、最も親しい友人が苦しんでいる。それが彼女にさらなる無力感と罪の意識をもたらした。
シャユラは目の端でアイシャの顔を見た。その表情には励ましと心配の色が浮かんでいる。「ガーディアンに向いていない者もいるのだろうか?」シャユラは疑問を口にした。テーブルのせいでその声はくぐもって響いた。
「それは…」とアイシャが言った。彼女のためらいがトゲとなって突き刺さる。
「自分には向いていないのかもしれない」シャユラは勇気を振り絞って認めた。その言葉が口から出ると同時に、彼女の心臓の鼓動が早くなった。そして肩に回されたアイシャの腕を感じると、鼓動が安定した。シャユラは友の温かい抱擁に安らぎを感じていた。
「だとしても問題ない」とアイシャが言い、その一瞬、彼女はその言葉を信じた。その瞬間、疑念と罪のナイフが鋭さを失ったような気がした。だがそれも一時的なものにすぎなかった。
「だからこそイコラと話すべきだ。彼女は知っている。彼女は理解している」
「飲み物だ」
その声がシャユラを目覚めさせた。リード7の連結式の関節の動作音と、アーマーのガチャガチャという音が聞こえる。
「…熱いぞ」
「お前のはシナモン入りだ」とリードが言うと、シャユラは力を振り絞って彼に向かって中途半端に親指を立てた。
「スロアンのことで怒ってることは知っている」とリードが言うと、突然シャユラは心配になり、再び鼓動が早くなった。彼は他にも何か言ったが、彼女には、耳の中の激しい血液の流れと、胸の中の激しい鼓動音しか聞こえなかった。
彼が自分の返事を待っているかもしれないと考え、シャユラは適当に言葉を挟んだ。「ありがとう」と彼女は弱々しく言った。リンゴとシナモンの香りが彼女に突き刺さった。タワーの中でガーディアンとして、アイシャやリードと出会った頃の初期の記憶が蘇ってきた。シャユラは座り直すと、蒸気の上がっているマグカップを両手で掴み、今にも沸騰しそうなリンゴ酒を自分のもとに引き寄せ、その幸せな時間の香りを吸い込んだ。
「分かってる」とシャユラがようやく小さな声で決まり悪そうに言った。彼女は自分が何を指してそう言っているのか分からなかったが、それが彼らの求めている言葉だと推測した。「すまない」
「我々に謝る必要はない」とリードが言った。「レイトカと彼のゴーストに謝るべきだ」レイトカという名前を聞いて、複数の罪の刃がシャユラの胸にねじ込まれた。彼女はシナモンとリンゴの香りを再び深く吸い込んだ。彼らは友人だ、それを忘れるな。自分の家族なんだ。彼女は降参した。
「あれはタイタンでのことだった」とシャユラはようやく口を開いた。彼女は真実を打ち明けることをためらった。自分の恐ろしい妄想を掘り下げるのは気が進まなかったのだ。「私はタイタンにいた。光なき者だった時と同じように、ハイヴに囲まれていた。そこにナイトがいた… 私が何度そのナイトを倒しても、奴は復活し続けた。私はそこで死ぬべきだった」
「だがそうはならなかった」とアイシャは言った。シャユラはアイシャが自分の手にその手を重ね、強く握りしめるのを感じた。まるでそれが自分に起こったことではないように感じたが、それでも安心することができた。「私たちは光を取り戻した、そして――」
「暗黒が迫ってきた時に何が起こる?」シャユラは答えを知りたかった、だがリードやアイシャがその質問に答えられないことを知っていた。「彼女は再び光なき者になるのか? ひとりきりで」環境都市で孤独に死を迎えるスロアンを想像して彼女は内臓をえぐり出されるような思いがした。
何も言わずにリードがアイシャの手の上に自分の手を乗せた。それだけだったが、それで十分だった。