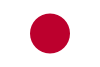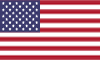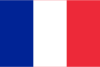Related Collectible
Lore
伝説の古豪のヘルム
「どこかに最後の安全な都市がある。そう信じるしかない」
「最後の安全な都市」は名ばかりの都市だ。私はこの場所で、大崩壊以前の失われた大都市が見つかると思っていた。だが代わりに見つかったのは、焚火の周りに密集したテントや組み立て式の避難小屋の海だった。ここに住む者たちは、トラベラーの影に隠れていれば安全で、魔の手が人類に及ぶことはないと思い込んでいる。私の目に映るのは、何百キロにも及ぶ、雪を頂いた険しい山々だけだ。私の指に残るのは、霜焼けの感覚だけだ。そんなもので誰も止められやしない。足止め程度にしかならないだろう。
私は入植者のキャラバンとこの場所に来た。山々を登る行進は私が今まで生き延びてきたどの戦いよりも辛かった。負傷、飢餓、そして低体温症で何百人も死んだ。お馴染みの厄難が勢ぞろいだ。死者は道沿いに埋めた。墓標を立てたり、葬儀を行う時間はなかった。ここにいる蘇りし者の中には、人々を護衛する警備パトロールを組む話をする者たちもいる。そんなことをして何になる。敵はいずれ蟻たちを辿って巣を見つけに来るはずだ。総攻撃を受けてしまえば、我々に生き残る術はない。
日に日に蘇りし者たちが増えていく。彼らは組織化し、計画を立て始めている。彼らの存在に不安を感じずにはいられない。あの記憶が頭から離れない。弾薬や食料を求めて居住地を襲う集団、反抗する者たちの大量処刑、街全体が瓦礫と化す光景。ここにいる蘇りし者たちはウォーロードとは違うように見えるが、だからといってあの時のことを簡単に忘れることはできない。ここにいる他の入植者たちは、「シティ」の外に住む者たちのように、「あるべき世界」という自分たちの考えに囚われている。多くの人々が脱出を計画し、手に入る船に乗って地球を捨てようとしているのを耳にする。まるで地球以外ならこの太陽系は安全だとでも思っているかのように。他の者たちは、明確な継承と指導体制の確立を望んでいる。そして、私のように、自分の武器を信じ、事が始まるのを待っている者たちもいる。我々は戦争が避けられないことを知っている。
何かが我々全員を殺すだろう。これはもはや時間の問題だ。安全な場所などどこにも存在しない。今はもう。