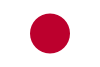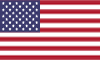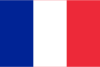Related Collectible
Lore
宇宙遊泳のフード
テクノロジー | 直通 | 124 | ――またコンテナが融解した。どの洗浄剤なら安全なんだ? 毒ガス事件の二の舞は困るぞ、イシュトヴァーン。
到着から6日が経過した。
鉄が唸り声を上げ、送電線がブーンと音を立て、パイプの中で何かがカサカサと動き回る。
ヤラスキスは4本の腕にスクラップを抱えながら瓦礫をよけていく。彼女はついにドレクの体格から成長することができ、下腕も爪の先まで再生していた。それでも、まだこの新たな我が家の狭いシャフトを行き来できる大きさだった。
皆、この破損した大昔の軌道ステーションは修復可能だと思っている。施設には長い間住人がいなかったようだが、それでもヤラスキスは時たま背後を確認しなければいけないという衝動に駆られた。
頭上から機械音声が聞こえてくると背筋に悪寒が走る。カルルホによると、機械音声は人間のために残された古いメッセージらしい。心配することは何もないはずだが… それでも気味が悪いと感じてしまう。
作業場にたどり着いてホッとする。彼女はドアの枠を蹴る。「スクラップを持ってきた」
カルルホはヤラスキスよりも小さく、今もドレクの大きさのままだったが、目を8つ持って卵から孵った彼は注目の的だった。100万人に1人の色男だということだ。それに彼は頭が切れる。彼は計画の立案者の1人だった。ヤラスキスはそんな彼と卵の頃から一緒だったおかげでここにいる。
カルルホはスクリーンから顔を上げずに手で示した。「適当に置いてくれ」
ヤラスキスに言わせれば、作業場は施設の中でも特に気味の悪い部屋だった。床に固定された鉄の机が大量にある。この部屋を作業場にするためには、山積みになった空のベックスの体を運び出さなければならなかった。ヤラスキスは何にも触れないようにスクラップを置く。
「何やってるんだ?」
「古い機械設計図を分析してる。システムに繋ぐことさえできれば、地表にいた時と同じくらい役に立つものが見つかるはずだ。そしてこの場所にはベックスがいない。ハイヴも、光の戦士もな」
「ケルも」ヤラスキスが力を込めて言った。
「ケルも」カルルホが繰り返す。「そして、この設計図が間違っていなければ、エーテルに困ることもないはずだ。この機械は2つの部品からできている。ひとつはエネルギーを収集し、もうひとつがそれを消費する。サービター用に収集器だけ流用できれば、一生エーテルの心配をしなくてもすむ」
彼はひとつのスクリーンを彼女のほうに傾ける。
生命の源となるエーテルをこの冷たく、暗い場所で作ることができるのであれば、エウロパから脱出したときに圧倒的な恐怖を感じ、施設が生活可能な空間になるまで危険な障害を慎重にかいくぐってきた甲斐があったと思えてくる。
ここでは、理解することができないエンジニアリングの会議から追い出されることはあっても、命令に背いたからといって、誰もヤラスキスの腕を切り落としたりはしない。
彼女は下腕を動かし、自分たちの未来を学ぼうと前かがみになった。