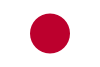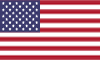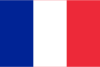Special Perks
Related Collectible
Lore
付き纏う幻影のクローク
V - お前は縛られている。
「どこへ行きたいんだ?」放浪者のジャンプシップが背後で激しい音を立てながら止まっている。エンジンが点火せず、今にも爆発しそうなほど騒々しい。それとは対照的に、エリスの船はその横で心地よい音を立てている。
「暗黒は互いに繋がっている。そしてその先にある何かとシグナルを送り合っている」エリスは自分の声がエンジン音にかき消されないように近づいて言った。「他のピラミッドにもっと詳しい情報があるかもしれない」
放浪者は舌打ちし、いぶかしげに片眉を上げた。「あのカルスが月の上に止まってることを考えると、少し危なくないか? 近寄らないほうがよさそうだ」
「ああ。だが、ガーディアンたちが今、サバスンの玉座の世界にあるルラクのピラミッドに向かっている。敵の目がそちらを向いている隙を利用する」
そう言うとエリスは彼の横を通り過ぎて船に向かった。「行くぞ」
「…先に何か食わないか?」
***
エリスと放浪者が玉座の世界のピラミッドと瘴気地帯が交わる地点の近くにある湿地帯でキャンプの準備をしていると、ピラミッドの方から身体を揺らすほどの轟音が鳴り響いた。霧の中から現れた巨大な船は、その端が見えないほど大きかった。
放浪者の顔が、滅多にないほど緊張で強張っている。片手でトラストを構え、もう一方の手には拳いっぱいのステイシスが握られている。
エリスは布で覆われたエグレゴアの茎を、悪臭を放つ沼地から突き出ているピラミッドの破片に乗せる。布を開き、その角をきれいに広げると、背後で放浪者の足音がした。
「何かに見られている」放浪者が呟いた。彼は変造されたゴーストのほうを振り返ると、エリスに聞こえていないことを確認しながら小声で囁いた。「彼女から目を離すな」そして大きな声で言った。「辺りを探索してみる。スクリーブを見逃していないとも限らないからな」
放浪者のゴーストは単音を発して了解の意思を示すと、エリスに視線を向けた。
「ジャーメーン」
彼は止まった。表に出そうとはしないが、放浪者という顔を演じる彼の行動には高潔さが隠されていることをエリスは知っていた。シールドは赤みがかっているが、彼女はその汚れの層の下にある彼の本質を見抜いていた。
「すまないが… 火を頼めるか?」
「了解」彼がトラストでソーラーの光を照射すると、ピラミッドの床で火花が発生し、エグレゴアが炎に包まれた。「すぐに戻る」
エリスは湿地帯に消えていく彼を見送ると、立ち上るエグレゴアの煙に視線を移した。
***
エリスは疲れきった様子で、地面に置かれた温かいクッションに腰掛けていた。放浪者は立ったまま、危険なほど大きく燃え上がる火の監視をしている。その火が、ハイヴ製の大鍋のような容器からシチューの甘い香りをすくい上げていた。エリスは放浪者から灰色がかった粘度の高い液体の入った不格好な器を渡され、顔をしかめた。
「何を見つけた?」放浪者はそう言うと、音を立てながらそれを飲んだ。
エリスはこの「食べ物」を唇に当てて、その温度と味を確かめた。前にシティに行った時にイコラからもらった、臭いの強い塩漬けのチーズに似ているが、これはかなり泥臭い。彼女は顔を歪ませると、食べる代わりに会話することを選択した。「予想していたとおりだ。彼らは繋がっている。おかげで分からないことが増えた」
「物事っていうのはそういうもんだ。藪を突っついたりせず、大人しく家に帰ったほうがいい」放浪者はそう言うと、音を立てながらもう一口飲んだ。
「エグレゴアが複数の暗黒を繋げてピラミッドと共振している。内容は解読できないが… 月のピラミッド、エウロパのピラミッド、グリコンとリヴァイアサンはどれも同じ相手と対話している。つまりルラクとカルスの話し相手は同じだということだ。これは… かなり危険な状況だ」
「なるほどな」放浪者はそう言うと口笛を吹いた。彼は首を振ると、彼女の器の中身が減っていないことに気付いた。「食わないのか?」
「いや…」エリスは彼が話を聞き逃したのかと思ったが、もう一度言っても無駄だと理解した。「…これは何だ?」
「かなり旨いぞ。上手く作れたのは今回が初めてだ。たまには誰かの手料理を食うのも悪くないだろう。なにしろ… お前は料理が苦手だからな」
「おい、何を食わせるつもりだ?」彼がさきほど狩っていたものを思い出し、気分が悪くなった。エリスは吐きそうになって口を開けながら放浪者をじっと見る。放浪者が前に食べたことがあると言っていたあれこれを思い出し、さまざまな考えが頭をよぎった。「腐ったスクリーブを料理したな」
「なに!?」放浪者はシチューを詰まらせて咳き込んだ。「そんなものを出すはずがないだろう、ムーンダスト」彼は笑った。「ザリガニのシチューを食ったことがないのか?」放浪者はそう言いながら器を口に寄せ「あるいは、それに似た何かを…」と息を切らしながら付け加えた。「湿地帯に生息する小さなエビだ。旨いぞ!」
エリスは想像するのをやめて息を吸うと、放浪者を睨んだままそれを飲み込んだ。彼女の萎縮した胃に暖かさと同時にその液体が流れ込んでくる。エリスは緊張感がほぐれていくのを感じた。そのシチューの味は臭いとは比べものにならないほど素晴らしかった。彼女は笑みを浮かべて、もう一口飲んだ。
「ありがとう… 悪くない」