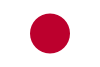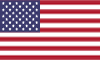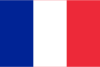Related Collectible
Lore
ピュロスのグラスプ
「もっとやれたはずだ。もっとやらなければならなかった」――人間のハンター、アイシャ
シミュレーション再構築ログ//LA-01-03//シティ、タワー、バザー
シャユラとアイシャは、タワーを中心とした敷地に張られたテントの中で、円形のテーブルの周りに散らばっている、真紅と朱色と金色のクッションの上に座っていた。沈む太陽が氷に覆われた格子を通して、2人の背中を明るく照らしている。頭上には、死者の祭り用の派手な飾りがいくつかぶら下がっており、テントの外にはさらに多くの飾り付けが施されていた。それは波乱に満ちた時代の中で生まれたコミュニティの礎だった。
「気分はどうだ?」アイシャが膝に肘をつきながら体を乗り出して質問をした。シャユラは答えなかった。
アイシャは通りの反対側の食料品店に並んでいるリード7を見ていた。「イコラとはまだ話してないのか?」彼女は再び質問した。ウォーロックは手で髪をかきあげて溜息をつくと、前屈みになってテーブルの上に頭をのせた。
「まだだ」シャユラがようやく答えた。「話すつもりではいる。すまない」
「謝る必要はない」アイシャはそう言うとシャユラに身を寄せ、励ますようにその肩に手を乗せた。「当然だ。私たちは多くの困難を体験した。対戦に参加する前に、シャユラがどれだけ苦しんでいるか、もっと気を付けて見ておくべきだった。それを知らずにすまなかった。怒鳴ってしまったことも謝る」
シャユラはアイシャの姿を目の端で捉えた。彼女が顔を逸らして髪の毛から手を離すと、その髪の毛がカーテンのように彼女の顔を隠した。「ガーディアンに向いていない者もいるのだろうか?」シャユラは疑問に思った。テーブルのせいで彼女の声はくぐもって聞こえた。
アイシャはどう答えたらいいか分からなかった。「それは…」
「自分には向いていないのかもしれない」シャユラは頭をテーブルに乗せたまま言った。アイシャは体を乗り出し、友人の肩に腕を回した。
「だとしても問題ない」とアイシャは言った。「だからこそイコラと話すべきだ。彼女は知っている。彼女は理解している」
シャユラは再び黙り込んだ。シャユラの背中越しにリードの姿が見えた。大きな手で蒸気の上がる複数のマグカップを運んでいる。
「飲み物だ」とリードは言うと、テーブルの上にマグカップを置いた。アイシャは礼の代わりに、励ますような、だが緊張を滲ませた笑顔を彼に向けた。「気をつけろ」リードがそう言うと、彼女はマグカップに手を伸ばした。「熱いぞ」
「お前のはシナモン入りだ」と彼はシャユラに言った。彼女はテーブルに頭をのせたまま親指を立てた。アイシャは何も言わずに心配そうな表情を浮かべてリードのほうを見ると、首を振った。彼が席を外している間、2人の会話は暗礁に乗り上げていた。
「スロアンのことで怒ってることは知っている」とリードは言った。「ただ、司令官はできることは全てやっている。我々もそうだ。自分を責めるな、その――」
「ありがとう」とシャユラは顔を上げずに言った。彼女は姿勢を変えて両手でマグカップを掴むと、今にも沸騰しそうなリンゴ酒を引き寄せた。彼女はマグカップを覗き込むような格好になると、シナモン、蜂蜜、リンゴ、そしてクローヴの香りを吸い込んだ。彼女は周りを見渡してから目を閉じた。どうやら、先ほどよりも意識がはっきりとしてきたようだ。
アイシャとリードはゆっくりと深呼吸をした。そしてシャユラに呼吸をする時間を与えた。「分かってる」とシャユラがようやく小さな声で決まり悪そうに言った。「すまない」彼女がスロアンのことを言っているのか、自分の態度のことを言っているのは分からなかった。
「我々に謝る必要はない」とリードはアイシャを見ながら言うと、アイシャはそれに同意するようにうなずいた。「レイトカと彼のゴーストに謝るべきだ」
「あれはタイタンでのことだった」とシャユラはマグカップに目を落としたまま、ようやく説明を始めた。リードとアイシャは顔を見合わせたが、どちらも口を挟まなかった。要点にたどり着くまで、シャユラのペースに任せることにした。「私はタイタンにいた。光なき者だった時と同じように、ハイヴに囲まれていた。そこにナイトがいた… 私が何度そのナイトを倒しても、奴は復活し続けた。私はそこで死ぬべきだった」
「だがそうはならなかった」とアイシャは言うと、テーブルの反対側から手を伸ばし、安心させるためにシャユラの手を力強く握った。「私たちは光を取り戻した、そして――」
「暗黒が迫ってきた時に何が起こる?」シャユラが質問した。だが彼女はリードやアイシャがその質問に答えられないことを知っていた。「彼女は再び光なき者になるのか? ひとりきりで」
リードとアイシャは顔を見合わせた。エクソはテーブルの向こう側から手を伸ばすと、アイシャが握っているシャユラの手の上に大きな手を置いた。リードは何も言わなかった。アイシャは目の前にいる彼に笑顔を向け、感謝の意を示した。この3人のファイアチームは彼らにとって家族だった。アイシャはとにかく、この家族が暗黒を乗り越えられることを願うしかなかった。
たとえ失敗したとしても、挑戦するだけの価値があることを。