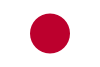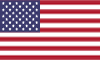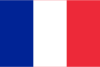Related Collectible
Lore
白熱のグリップ
夏季の宴2022で獲得した火種と残り火を使って、このアイテムをアップグレードしろ。
ナムラスクは織機の近くで4つの手を動かすが、機械自体に触れるようなことはしない。自分のように技術に劣る者が触れれば、その機構を穢してしまうような気がしたからだ。そもそもこれほど織機の近くにいられること自体、彼にしてみればとても信じがたいことであった。
「それで」背中越しにデジタルな声が尋ねる。「どうだ?」
彼はサッと横へ避け、エイダ1と視線を合わせた。織機を見に来ないかと言ってきたのが、このエクソだった。「見事な機械だ。その扱いを完全に習得するのは難しいのだろうと思う」
「シンセウィーブは… たしかに面倒ではある」エイダは肯定した。彼女は小さな部屋を横切って、織機の姿をその目に収める。「だが、生み出される結果はその面倒に十分見合う」
「…なぜ」ナムラスクは勇気をかき集めて、抱えていた問いを口にした。「なぜ私をここへ呼んだのだ?」
「この織機が存在していること自体、お前の民のおかげだから」とエイダは答える。「そして、エイドからお前が織り手だと聞いたからだ」
その話にナムラスクは不意を突かれた。エイドは彼を避ける傾向があり、嫌われているものとばかり思っていたからだ。もっとも、仮にそうだったとしてもナムラスクに彼女を責めることはできなかった。
「そうだ」ナムラスクは言った。そしてほとんど聞こえない音量で「今は」と付け加えた。
彼は黙り込み、首を垂れてその恥に耐える。
エイダは何も言わなかったが、少しして物憂げな眼差しで織機の方を見た。「ブラックアーマリーの炉が失われたとき、私は自分自身が何者なのかわからなくなったような気がした。だから私は… 自分を見つめ直さなければならなかった」
エイダはナムラスクの傍を離れ、自分の机の引き出しを開けて、その中から布にくるまれた物体を取り出した。
「これを」彼女はそう言って彼にその物体を手渡した。「練習用に使うといい」
ナムラスクは包みを開く。そして目を見開いて、自分の手にあるシンセウィーブ・ボルトをまじまじと見つめた。
「同じ織り手へと贈り物だ」エイダは優しげな声でそう言った。