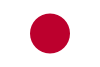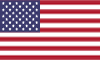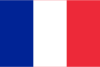Related Collectible
Lore
獣狩りのグローブ
因果の糸を手繰り寄せろ。
II
「今は避けることができる戦いだと言ってるだけです。スパイダーは彼らに大した褒美は与えていません」シャクトは死ぬリスクを冒すほどじゃないということを言おうとしていたが、何度も彼女の飢えた抜け殻を見てきた彼にとって、それが誤りであると分かっていた。生命の維持がかかっていれば死ぬ覚悟はいつでもある。それに、彼女にとって、闘技場を壊すのは百の命を犠牲にするに値するものだった。
「私たちにとっては大した褒美だ。本人がいなくても、ドリクシスに痛手を負わせることはできる。エーテルがなくなれば、忠誠心もなくなり、戦いも終わる」
「彼が直接来ているとは限りません。何にせよ、ドリクシスはアヴロックに仕えています」シャクトは通信機から流れる自分の声を張り上げ、彼女のヘルメットを振るわせて耳で反響させた。「彼を直接攻撃するべきではありません。少なくとも今は。スパイダーの気を引いてしまうことになります」
トリンは手のひらをヘルメットに叩きつけて耳鳴りを消そうとした。「お前が許可することだけをやってたら、きっと今頃は半分の武器とわずかな知識しか手にしてない」彼女は下に渓谷にある粗末な野営場を見下ろせる尾根でパイクのエンジンを切った。
「そういうことではありません」シャクトは降りながら言った。
下には6つのパイクがまとめて停車してあり、エンジンはまだ金属が冷え切ってはいない。スパイダーのトゲが目立つ1体のサービターが、縦に突き出た岩場付近の小山にどさりと座り込んだ。途切れ途切れにパワーを放出し、催眠術的な光を放っている。
「変ですね」シャクトは前方に浮遊しながら言った。周囲をぼんやりと照らす光が、彼の背後の星々や虚ろな空間へと消えて行く。トリンは彼を見ないまま降りて、喋りだした。
「多ければ多いほどいい」
「サービターがいるということは、かなり重大なことみたいですね」
「ドリクシスだろう。あれは上級アソシエイトのパイクだ」
「アヴロックか、あるいは他の者たちのものかもしれません。いいですか、トリン。もしあなたがスパイダーの配下を殺して彼のものを強奪しようとしているのがバレたら、彼はエンフォーサーを仕向けてきます。そうした事態は避けないといけません」
「それは奴らが生き残れたらの話だ」
「彼らが全員死ねば誰がこちらに向かってくると思いますか? あなたはまだそうした戦いに臨むべきではありません」
彼女は膝を付いて誰もいない野営地を調べた。「なら、もう少し待って誰が来るか見てみよう」
騒ぎが単調な静寂を破る前に朝がやってきた。トリンの瞼は開いては閉じ、回転のぞき絵が切り替わるように夢の狭間と地平線に光が満ちるのを交互に見た。
「あそこです」シャクトの声が周囲を包み込むようなリーフの唸りをわずかに上回る。
トリンは身体を前のめりにして尾根から覗き込んだ。下の渓谷では先端が曲がり、折られてしまった羽根で飾り立てられたエリクスニーのキャプテンが、片腕で地面を這っている。エーテルガスと液体が、マスクと装甲の損傷から溢れている。
「ドリクシスじゃない」トリンの言葉には失望と安心が入り混じっていた。
「ええ」
「でも奴の仲間であることに間違いはない。あの先端が赤い羽根は見覚えがある」
「部下ですね。その方が私たちにとっても好都合です」
「何が起きたんだ?」
「周辺を移動した様子や武器を使用した形跡は見受けられません」シャクトが微かな戸惑いを含んで鳴いた。
「誰だか分かるか?」
「ここからですか? 顔を地面に突っ伏してるのに?」
トリンは立ち上がり、ローブからほこりを払った。「もっと近くへ行ってみよう」