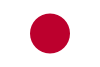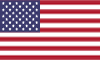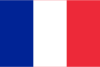Exotic Perks
秩序の祝福
Stats
| 防御力 | 0 |
Curated Roll
Lore
アセンブラーのブーツ
偽りの光子と不可能な計算の明示。
I.
イコラ・レイは怒っていた。彼女は昨夜発生したエリクスニーの野営地での破壊工作に関する報告を終えたばかりだった。そのことを考えれば考えるほど、彼女の耳の中で心臓の鼓動がさらに力強く鳴り響き、指先で光がジリジリと音を立てた。今にもその怒りによって、高所の通路を大またで歩いている彼女の体は浮かび上がりそうになった。
突然、聞き覚えのある低い声が聞こえた。「怒りは精神を乱す、重力が時空を曲げるように。それは歪みのひとつの形態だ――役に立つ、だが危険でもある」イコラは、多分オシリスだろうと思いながら振り返った。だがそこには彼女しかいなかった。
「重力のように、怒りは臨界点に到達するとその重みによって自壊し、光すら逃げられなくなる」イコラはひとりで微笑んだ。目の前にいなくても、彼女の助言者は常に何を言うべきかを知っていた。
イコラ・レイは身をかがめて小部屋に入ると、タワーの冷たい石にもたれかかって座った。彼女は目を閉じると自分の呼吸に耳を傾けた。そして心拍数を安定させることに意識を集中させる。イコラは自分の体から力が抜けていくのを感じた。
彼女は冷静さを取り戻すと、訓練を始めた頃にオシリスから教わった瞑想を行った。彼女は自分の体を流れる光を感じた。最初は激しい炎だったが、やがてそれは川の流れとなり、最後にはそよ風へと変わった。目を開ける頃には、その精神は研ぎ澄まされていた。
彼女には敵と戦う準備ができていた。
II.
セイント14が軍用品の整理をしていると、オシリスが部屋に入ってきた。セイントはグレネードの入った箱の隣にデータパッドを置いて立ち上がった。オシリスは何かを探すように、銃と弾薬の棚を見渡した。
セイントは立ったまま何も言わずに、声をかけられるのを待った。声をかけるつもりがないことに気づき、彼のほうから呼びかけた。「オシリス、何を探しているんだ?」その声は大きく、緊張していた。
オシリスは棚から視線を逸らさずに言った。「サイオンがザヴァラのゴーストに使った光のサプレッサーを探している。研究に必要なんだ」
「ザヴァラが持っているはずだ。本人に聞いてみろ」セイントは平静を装って言った。
オシリスがパートナーのほうを振り返った。彼は考え込むように目を細めている。「そうか」と言うと、少し考えてから続けて言った。「ありがとう」
出ていこうとする元ウォーロックの背中に向かってセイントが声をかけた。「近いうちに一緒に何かしたいと思っていたんだ。2人だけで」
「してみたいって、何をだ?」とオシリスは微笑を浮かべながら聞いた。
「アルプスに行くのも悪くない」とセイントが提案した。「それかプラハの遺跡を散歩するのもいい。昔みたいにな」
「悪くなさそうだ」とオシリスが言った。彼は肩をすくめた。「我々の不在中にシティが焼け落ちさえしなければな」そして少し間を置いてから言った。「それだけか?」
それだけ? セイントはヘルメットの中で眉をひそめた。「ああ」
心の奥底で無力感を覚えているセイントをその場に残し、オシリスは大またで部屋から出て行った。
III.
ラクシュミ IIは騒々しい中庭の反対側からオシリスを観察していた。タワーにいる政治的な生物の中で、彼こそが彼女にとって一番厄介な存在だった。
彼女が懸念していたのは、この元ウォーロックの不確定要素ではない。むしろ、その反対だった。
デバイスは彼の尊大な能力をしっかりと分析していた――彼のあらゆる行動は標準偏差内におさまっていた。
変人としての名をほしいままにしていた人物にしては、最近の動きはどれもひどく穏やかだった。突飛ではない彼の最近の行動が、彼女を悩ませていた。
ゴーストを失ったことが、想像以上に影響を及ぼしているのだろうか。定命者としての責務が彼の精神を弱体化させたのかもしれない。
オシリスこそがベックスのデータセットの盲点を表している可能性も考えられる。人間にしか理解できない何か。あるいは、ベックスが見ればすぐ分かるようなものでも、人間が無意識に見落としてしまうような何かかもしれない。
いずれにしても、昔ながらのやり方でオシリスを観察する必要がある。少なくとも彼の有用性が尽きるまでは。