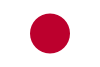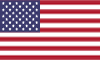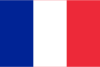Related Collectible
Lore
崇高のクローク
我々は共に築き上げる未来を祝う。
シティは変わった。少なくともクロウにとってはそうだ。仮面の記憶は今も彼の顔に押し当てられているが、今は胸を張って歩くことができる。そして、夏季の宴の焚火の前を通れば、彼はいつだって迎え入れられる。
彼はこの祝祭が亡き者たちを偲ぶためだけではなく、手を取り合っている者たち、そして彼らと共に築き上げる未来を称えるためにあることを知っている。クロウは今、友情について考えていた。
クロウの持つ人間関係の多くは、彼が見つめる先でパチパチと音を立てる焚火の丸太のように、いろいろな理由で部分的に焼け焦げてしまっている。その中でも、ケイドとの関係が一番彼の心に残っていた。彼はクロウとしての新たな人生を生きる中で、別の時に、別の場所で芽生えたかもしれない友情だけでなく、ケイドがどのような人だったのかについて考えるようになっていた。そして、今この瞬間に考えるのは、このように思いを巡らせているクロウについて、ケイドが何と言うだろうか、ということだった。
おそらく、「前に進み続けろ」とでも言うだろう。だが、その次はどうする?
「人とどう接したらいいのかわからない」クロウがグリントに向かって言った。「馬鹿げているかもしれないが、私は… ガーディアンではない人たちとどのように会話をすればいいのかを忘れてしまったんだ」
優しい振動音を出すグリントの瞳は、夜空に浮かぶ閃光のように明るかった。「教室に通うのはどうでしょうか?」彼は思慮深げに言う。「人間関係の教室ではなく、陶芸教室とか?」
クロウが心の中にあの閃光を感じて笑う。それは彼の肩にのしかかる重荷よりも軽かった。彼はグリント、バンガード、そしてまだ出会っていない者たちと、未来を築き上げることができる自分が幸運だと思った。「よし、何か新しいことをして――」彼は1歩踏み出す直前で躊躇する。「タワーのハンガーを散歩してくるか。私が知らない技を知っている者がいるかもしれないしな」
立ち止まってはだめだ。前に進み続けなければならない。
そうすれば、ケイドも喜んでくれるだろう。